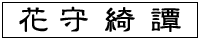二月寓話 2
2.
雪がまばらに舞う曇り空の元、三者三様で住宅地を歩いた。上機嫌な颯斗と、少し遅れてついてくる不機嫌オーラ全開な煌と、そしてそれを気遣いながら颯斗から離れられないでいる夏と。
「すっげぇなぁ。よくもこんなにびっしりと家を建てたもんだ。家だらけじゃねぇか。本当に人間のための街だって気がするなぁ」
「君んちはこうじゃないんだ」
「おう。うちは山ん中だからな。人間の方が大自然を間借りしているって感じだ。聞いて驚け、最寄の駅まで歩いて一時間半だぞ」
からからと笑って、颯斗は言った。
確かに颯斗には山の緑がよく似合う。
申し訳程度に開かれた道をしなやかな健脚が駆けて来る。夏も盛りの青い空。ひそかに雷をはらんだ雲が白い宮殿を作る。木漏れ日に見る明暗と、草いきれの記憶。息を調える間もおしむように少年が何かを言うと、幾重にも重なる梢の上で、猛禽がいななくと共に羽音を刻んだ。
途端に、次々とわきおこるイメージに瞑目する。そうでもしていなければ記憶の大洪水に押し流されてしまいそうだ。
「ねえ、湖はある? たくさんの木に囲まれた水辺」
ふいに、夏の口が言った。
まただ、今日はおかしい。考えるよりも先に体が動いてしまう。
なんなのだろう、これは?
頭の片隅では異変を察知した何かが警告を発しているというのに、それでも夏は、期待に胸を膨らませながら颯斗の答えを待ってしまう。
「湖? 池や沼ならぽつぽつあるけど……あと、木なら腐るほどある。でも、湖っていうほどのものはないかなぁ。もっと具体的な目印はないのか?」
「具体的って、それは……大きな木、木の王様がある……」
颯斗の首がわずかに傾いだ。
だめだ、こんなふうでは伝わらない。気ばかりが急いて、イメージばかりが先に立って、何ひとつ思い通りに伝えることができない。
言葉は苦手だった。
「ごめん。多分昔住んでいたところ。子供の頃だからよく憶えてなくて。ごめん、何故だか聞いてみたくなった、それだけだから」
颯斗はほんの少しだけきょとんとしていたが、すぐに何事もなかったかのように笑った。夏はほっとして、自然に顔がほころぶのを感じた。
十字路で案内図を確認すると、どうやら目的地はこの坂を上りきったところになるらしい。
「ねえ、何をしに来たのさ。旅行?」
「旅行じゃないなぁ。人探しかな? 連れの友達って奴に会いに来たんだ」
友達、そう聞いた夏は、胸のあたりに小さな疼きを感じた。そうだ、颯斗には颯斗の生活がある。家族がいて、交友関係がある。夏はたった今会ったばかりの、 せいぜい顔見知りとでも言うしかない、行きずりの道案内にすぎない。役目を終えてしまえば、颯斗との係わりはそれで終わりなのだ。
雪が舞う。けっして強くはならず、かといって降り止むことも無く、ひらひらと鉛色の空から舞い降りてくる。
木々に。屋根に。庭に。颯斗の髪にも。そして夏の肩にも。
三人で登る坂道は、夏がこがれてやまない、あの緑あふれる山の道ではなかった。頂上に突き刺さる不恰好なマンションを目指して登る。もう、数分もしないうちに颯斗を連れとやらに引き渡して、夏は煌と共に現実へと戻らなければならない。
どうしてこんな気持ちになるのか……
何故だか急に虚しくなって道の先を見た。
人影がある。電柱に背をあずけるようにして立つそれは、彼らが近づいてきたことに気付くと、すっと姿勢を正してこちら側に顔を向けた。
「遅い」
開口一番にそう言う。
「人のこと放っておいて、何ぬかしやがる!」
応えたのは颯斗だった。つまり、この少年が颯斗の連れということになる。
でも、彼は……
夏は記憶の中に答えを求めた。見覚えがある。色の薄い髪、涼やかな目元、夏の背が伸びたように、彼もまたずいぶんと大きくなっていたのだけれど。でも間違いない。きっとそうだ。
相手の少年も驚きは同じだったと見え、ほんの少しだけ夏の顔を凝視したかと思うと、ちらり、と颯斗の方に目を向け、そしてまた夏のことを見た。
少年は笑った。
そう、彼はいつもこういう笑い方をする。人によっては冷淡にも見えるらしい独特の笑み。
「久しぶりだね」
いくらか低くなったとはいえ、懐かしさを呼び起こすには充分な声が言う。
あの頃の夏にとって、ただひとり友達と呼ぶことができた存在。
道の頂に、青桐早智がいた。
雪がまばらに舞う曇り空の元、三者三様で住宅地を歩いた。上機嫌な颯斗と、少し遅れてついてくる不機嫌オーラ全開な煌と、そしてそれを気遣いながら颯斗から離れられないでいる夏と。
「すっげぇなぁ。よくもこんなにびっしりと家を建てたもんだ。家だらけじゃねぇか。本当に人間のための街だって気がするなぁ」
「君んちはこうじゃないんだ」
「おう。うちは山ん中だからな。人間の方が大自然を間借りしているって感じだ。聞いて驚け、最寄の駅まで歩いて一時間半だぞ」
からからと笑って、颯斗は言った。
確かに颯斗には山の緑がよく似合う。
申し訳程度に開かれた道をしなやかな健脚が駆けて来る。夏も盛りの青い空。ひそかに雷をはらんだ雲が白い宮殿を作る。木漏れ日に見る明暗と、草いきれの記憶。息を調える間もおしむように少年が何かを言うと、幾重にも重なる梢の上で、猛禽がいななくと共に羽音を刻んだ。
途端に、次々とわきおこるイメージに瞑目する。そうでもしていなければ記憶の大洪水に押し流されてしまいそうだ。
「ねえ、湖はある? たくさんの木に囲まれた水辺」
ふいに、夏の口が言った。
まただ、今日はおかしい。考えるよりも先に体が動いてしまう。
なんなのだろう、これは?
頭の片隅では異変を察知した何かが警告を発しているというのに、それでも夏は、期待に胸を膨らませながら颯斗の答えを待ってしまう。
「湖? 池や沼ならぽつぽつあるけど……あと、木なら腐るほどある。でも、湖っていうほどのものはないかなぁ。もっと具体的な目印はないのか?」
「具体的って、それは……大きな木、木の王様がある……」
颯斗の首がわずかに傾いだ。
だめだ、こんなふうでは伝わらない。気ばかりが急いて、イメージばかりが先に立って、何ひとつ思い通りに伝えることができない。
言葉は苦手だった。
「ごめん。多分昔住んでいたところ。子供の頃だからよく憶えてなくて。ごめん、何故だか聞いてみたくなった、それだけだから」
颯斗はほんの少しだけきょとんとしていたが、すぐに何事もなかったかのように笑った。夏はほっとして、自然に顔がほころぶのを感じた。
十字路で案内図を確認すると、どうやら目的地はこの坂を上りきったところになるらしい。
「ねえ、何をしに来たのさ。旅行?」
「旅行じゃないなぁ。人探しかな? 連れの友達って奴に会いに来たんだ」
友達、そう聞いた夏は、胸のあたりに小さな疼きを感じた。そうだ、颯斗には颯斗の生活がある。家族がいて、交友関係がある。夏はたった今会ったばかりの、 せいぜい顔見知りとでも言うしかない、行きずりの道案内にすぎない。役目を終えてしまえば、颯斗との係わりはそれで終わりなのだ。
雪が舞う。けっして強くはならず、かといって降り止むことも無く、ひらひらと鉛色の空から舞い降りてくる。
木々に。屋根に。庭に。颯斗の髪にも。そして夏の肩にも。
三人で登る坂道は、夏がこがれてやまない、あの緑あふれる山の道ではなかった。頂上に突き刺さる不恰好なマンションを目指して登る。もう、数分もしないうちに颯斗を連れとやらに引き渡して、夏は煌と共に現実へと戻らなければならない。
どうしてこんな気持ちになるのか……
何故だか急に虚しくなって道の先を見た。
人影がある。電柱に背をあずけるようにして立つそれは、彼らが近づいてきたことに気付くと、すっと姿勢を正してこちら側に顔を向けた。
「遅い」
開口一番にそう言う。
「人のこと放っておいて、何ぬかしやがる!」
応えたのは颯斗だった。つまり、この少年が颯斗の連れということになる。
でも、彼は……
夏は記憶の中に答えを求めた。見覚えがある。色の薄い髪、涼やかな目元、夏の背が伸びたように、彼もまたずいぶんと大きくなっていたのだけれど。でも間違いない。きっとそうだ。
相手の少年も驚きは同じだったと見え、ほんの少しだけ夏の顔を凝視したかと思うと、ちらり、と颯斗の方に目を向け、そしてまた夏のことを見た。
少年は笑った。
そう、彼はいつもこういう笑い方をする。人によっては冷淡にも見えるらしい独特の笑み。
「久しぶりだね」
いくらか低くなったとはいえ、懐かしさを呼び起こすには充分な声が言う。
あの頃の夏にとって、ただひとり友達と呼ぶことができた存在。
道の頂に、青桐早智がいた。
夕闇の迫る公園を夏は煌とふたりで歩いていた。雪はもう、降っていない。
煌が漆黒のフードをおろすと、そこから溢れ出た明るい栗色の髪が波打つ。細やかなウェーブの髪だ。夏とは似ても似つかない。眉の形も目の大きさも違う。似ているとすればただひとつだけ、小さくとがった顎のラインぐらいか。きっと、誰が見ても彼らを双子だとは思わないだろう。
煌はひとことも喋らなかった。夏が早智たちと語らっている間も、こうしてふたりで家路についてからも、ずっと。だから、夏も何も言わなかった。
少しずつ暗くなる道をふたり、無言で歩いた。
そうして公園も外れ、ニレの木立に差し掛かろうという頃になってようやく、煌は口をひらいた。
「そろそろ越しましょうか」
「言うと思った」
夏の口ぶりが気に障ったのか、煌の声が険を帯びる。
「この街も二年になるもの。わかっているでしょう? 私たちはひとつところに長くはいられないのよ」
それでもきっと、きっかけは早智なのだ。三年前もそうだった。
「煌は早智のことが嫌い?」
「違うわ。これは私たちの問題だもの。そうでしょう?」
「違うよ。ごまかしたってわかる。煌らしくないよ。あの時だってそうだ。いったい何があるのさ。僕には言えないこと?」
「おかしいのはあなたよ。いつもの夏ならそんなこと言わない。知っているでしょう? 私たちは”違う”の。うまくやらなければ大変なことになる。もしかしたら別れ別れになってしまう可能性だってあるのに」
あなたはそれもいいと言うの ?
煌の甲高い声に、五時半を打つ鐘の音が重なる。薄闇がふたりを隔てていて、表情をうかがうのは難しい。けれど、夏には見えるのだ。
煌の輪郭から浮かび上がる淡い色の光。淡紅色のゆらめき。
感情の波が見える。夏には見える。煌の心がゆれているのだ。
「やめよう」
夏は顔をそむけ、まぶたを伏せた。
「今ここでする話じゃないよ。僕らだけの問題じゃない。麗(うらら)にも聞いてみないと」
「姉さんは反対しないわ」
煌はフードをかぶりなおすと、ひとり先に立って足を早めた。
花のような光が少しずつ小さくなっていくのを、夏はしばらくのあいだ見つめていた。
煌が漆黒のフードをおろすと、そこから溢れ出た明るい栗色の髪が波打つ。細やかなウェーブの髪だ。夏とは似ても似つかない。眉の形も目の大きさも違う。似ているとすればただひとつだけ、小さくとがった顎のラインぐらいか。きっと、誰が見ても彼らを双子だとは思わないだろう。
煌はひとことも喋らなかった。夏が早智たちと語らっている間も、こうしてふたりで家路についてからも、ずっと。だから、夏も何も言わなかった。
少しずつ暗くなる道をふたり、無言で歩いた。
そうして公園も外れ、ニレの木立に差し掛かろうという頃になってようやく、煌は口をひらいた。
「そろそろ越しましょうか」
「言うと思った」
夏の口ぶりが気に障ったのか、煌の声が険を帯びる。
「この街も二年になるもの。わかっているでしょう? 私たちはひとつところに長くはいられないのよ」
それでもきっと、きっかけは早智なのだ。三年前もそうだった。
「煌は早智のことが嫌い?」
「違うわ。これは私たちの問題だもの。そうでしょう?」
「違うよ。ごまかしたってわかる。煌らしくないよ。あの時だってそうだ。いったい何があるのさ。僕には言えないこと?」
「おかしいのはあなたよ。いつもの夏ならそんなこと言わない。知っているでしょう? 私たちは”違う”の。うまくやらなければ大変なことになる。もしかしたら別れ別れになってしまう可能性だってあるのに」
あなたはそれもいいと言うの
煌の甲高い声に、五時半を打つ鐘の音が重なる。薄闇がふたりを隔てていて、表情をうかがうのは難しい。けれど、夏には見えるのだ。
煌の輪郭から浮かび上がる淡い色の光。淡紅色のゆらめき。
感情の波が見える。夏には見える。煌の心がゆれているのだ。
「やめよう」
夏は顔をそむけ、まぶたを伏せた。
「今ここでする話じゃないよ。僕らだけの問題じゃない。麗(うらら)にも聞いてみないと」
「姉さんは反対しないわ」
煌はフードをかぶりなおすと、ひとり先に立って足を早めた。
花のような光が少しずつ小さくなっていくのを、夏はしばらくのあいだ見つめていた。