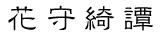
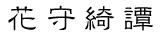
夏の前奏曲 〜プレリュード〜 2
「なんだ、あんた、まだへこんでるの?」
振り返らずともわかる。姉の朱音だ。この花守塾の中で颯斗のことをアンタよばわりするのは彼女をおいてほかにはない。
颯斗はゆるやかなまばたきにあわせ、ため息をひとつこぼすと、ふたたび外の景色に視線を戻した。
明け方のわずかな時間をのぞいて、今日はずっと雨が降り続いている。しとしとしとしとと鬱陶しいことこの上ない。昨日も一昨日も一昨昨日も空模様は似たりよったりだった。
このまま太陽がサボタージュを続けるのなら、いっそのこと嵐でも吹き荒れてくれないだろうか。そして、そこに何かしらのエネルギーが生じるかして、このとんでもない長梅雨を吹き飛ばしてはくれないだろうか。
被害さえ出なければその方がずっといい 颯斗は分厚い雨雲の向こうにまだ見ぬ夏色の空を想った。
「窓なんか開けて大丈夫なの? 雨が吹き込んだりはしない? アンタ、ここが図書室だって認識ちゃんと持ってる?」
ぽんぽんぽん、とテンポよく言葉を並べる。時に、受け手からはきついという批判の声が上がる朱音のもの言いだったが、本人はいっこうに気にしている様子はない。
放っておいてくれよな……と、軽く舌打ちながら、颯斗はがらがらと音のする年代ものの硝子窓を閉じた。確かに、いくらか風が出てきたようにも思える。
朱音はカウンターテーブルに片肘をつき、貸し出しノートに本の返却を記入していた。
さら、と彼女の動きに応じて艶やかな黒髪がゆれる。誰が見ても姉弟と知れる容貌のふたりだったが、髪の質だけは明らかに違っている。ある程度の長さで重み を持たせているものの、颯斗の髪は腰が強くて扱いが難しい。短くしていた時など、どうかすると針鼠のように広がってしまい手を焼いたものだ。幸い今日は湿 度とのおりあいが良いのか、つんつん具合も適度に落ち着いていた。
ただ、
颯斗の頭髪は精神状態のバロメーターだ
いつだったか、冗談交じりにそう言われたことがあった。むろん、その場限りのネタにすぎない戯言だが、何故だか颯斗の心には深く残っていた。
朱音に言われるまでも無く、颯斗の低調はじりじりと更新を続けている。
原因もわかっていた。
「姉ちゃんのところにも、高嶺からは連絡がないのか?」
「アンタのところにないのに、どうして私にあるっていうの」
高嶺が山を降りたのは三月も下旬、中学の卒業式を終えて十日ばかり経った日のことだ。
「落ち着いたら連絡すっわ」
そう言い置いたきり、未だになんの音沙汰も無い。
「だから、まだ落ち着き先が決まらないのでしょう?」
「もうじき四ヶ月じゃねーかよ」
「だって高嶺だもの。あんた、何年あいつと付き合ってきたの。無頓着っていうか無鉄砲っていうか、後先考えずに突っ走るのはお約束だったじゃない。そのくせ帳尻合わせは上手いから最後だけはなんとでもできちゃう。ああいうのって得よねぇ」
いや、まあ、それはそうなのだが……
あまりの言われように少しはフォローを入れようかと思ったのだが、朱音の主張が的確すぎて返す言葉が無い。許せ、高嶺。
高嶺と朱音と颯斗。彼ら三人はこの花守の里で育った。花守を含む旧八朔村(合併により現在は桃栗町)は県内でも指折りの過疎地である。
当然のこと何もない。いや、山ならば有り余るほどにあるのだから何も無いというのもおかしいのだろうが、人は往々にしてそういうのを何も無いと表すのだ。
高嶺は中学卒業と共に里を去った。
多かれ少なかれ常に子供たちの姿を見ることができるここ花守の里ではあるが、中学生ともなるとその数はぐんと少なくなる。進学するにも就職するにも先々のことを考えるとこの山里での展望は決して明るいとは言えないからだ。
里の方でも条件を満たしさえすれば子供たちの下山を承諾する。
親に望まれるものほど早くいなくなるのだ 時に颯斗はそう思うことがある。
颯斗たちの両親など、年がら年中仕事を理由にして日本各地を飛び回っている。はたしてあの二人は子供の存在や親子関係というものを何だと思っているのか。
そして高嶺はといえば、両親を相次いで亡くし天涯孤独の身の上だった。だから、それらの事情をあわせ見るとき、少なくとも高嶺が高校を卒業するまでの三年間は、自分たちの関係に大きな変化など起こるはずがないのだと、さしたる不安もなく安穏とかまえていた颯斗である。
それがある日突然、まさに晴天の霹靂。
「ちょっと外の世界でも見てくっかな」
そう言って高嶺は、あろうことか放浪の旅に出てしまった。