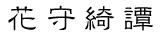
■ 男の子のつま先 3
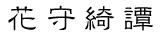
■ 男の子のつま先 3
早智と颯斗に違い、それは颯斗が言うところの“加害者”が、母であるか姉であるかということ――
颯斗も母の性格はわりと容認している。まあ、毎日顔を合わせる朱音とは違い、彼らの両親は、下手をするとその存在を忘れている日すらあるほどに遠い。だから、単純な比較で結論付けることはできないのだけれど、とりあえず颯斗は、彼にとって身近であり“生”である姉の朱音を苦手としていた。
いつだったか朱音に言われたことがある。
“何よ、なんでも自由になるくせに”
当時はピンと来なかったのだが、最近になって少しわかるようになった気もする。何もこれは朱音と颯斗に限った問題ではない。ただ、男と女を比べた場合、男であることの方が社会的には何かと有利な立場を得られるという事実。
たとえば中学のクラスメートである浅見奈々子、彼女が溜息まじりに語ったのは、去年も暮れが押し迫った頃のことだ。
「高校は商業校にするわ。就職にだって有利でしょう? うちは弟がいるし、親はあの子を大学にやりたいみたいだし、今の経済状態で二人続けて大学に出すっていうのは絶対に無理だもの」
父親のリストラが十三歳の少女を暗澹たる気持ちにさせたようだ。彼女は音大への進学を希望していたはず。当然のこと、家から通える範囲に大学など存在しない。どこへ行くにしても費用が嵩む、そんな世界だ、ここは。
幸いその後父親の再就職も決まり、彼女を取り巻く環境も、一時のどん底からは脱しているらしい。だからその心境にも何らかの変化が起きているかもしれないのだが、颯人は時々この時の言葉を思い出す。
男女平等だの雇用機会均等法だのフェミニストの皆さんの頑張りだの、社会はここ数十年で大きな変化を遂げてきた。けれどまだ、
―― 優遇されるのは男の子 ――
そんな声を聞くことも依然多い。
ただし、伽羅に限って言えば、出生率が高いのは断然男の方だったりするので、数の少ない女は珍重されているのも事実なのだけれど。
それでも、いつしかその背を追い越してしまった姉の、力で勝てるようになってしまった姉の、焦燥にも似たやり場のない憤りというものを颯人は感じている。朱音は隠しているようだが、わかってしまう。
社会的責任がどうだとか家族の大黒柱がどうだとか、男の側からすればもっと大変だと言いたくなるような事もきっとたくさんあるのだろう。でも、それらはまだまだずっと先のことで、未だ颯人の理解が及ぶところでは無い。
“なんだって、できるじゃない”
“どこへだって、行けるじゃない”
「そうは言ってもさ、姉ちゃん」
俺、何処へ行ったらいいのかすら、わからないんだけど――?
早い者では既に進路のことを考える者もいる。来年は受験生なのだから当然なのだが、颯人はこれまで何の展望も持てずにきてしまった。
里の年寄りたちは言う。
「最初の人生が華ぞ」
“最初”とは、彼ら伽羅たちのうちで、生まれた時に得た戸籍を手放すまでのことを言う。
変らぬ姿のまま人の世を生きていくことはできない。だから、彼らは時々小細工をする。
所詮戸籍など人が作り出した入れ物に過ぎないのだ。ならば必要な者が必要とする形で利用すればいい。人として規格外なら、それを自らの丈に合うよう逆に使い回してやれば良いではないか。
けれど、それでもやはり、生まれの証を手放すというのは、一度生まれ変わるということに他ならない。子供の頃の記憶。拙い願いを胸に、淡く甘く夢見ることが許されていた時間。たとえそれが叶うとも、叶うまいとも、名を変え、肩書きを変え、生きるために誰かとなり代わった途端、何か大きなものが指の間からこぼれ落ちてゆく。
だから懸命に生きよ――
何度もそれをくり返してきた先達は言う。
颯人は早智のことを思った。姉の朱音が「風のようだ」と評した同い年の友人。
早智は、ふっ、とした拍子に遠い目をすることがある。
本人にその自覚があるかどうかは知らない。けれど、あれは胸の奥に何か思うことを秘めている者がする目だ。もしもそんなことを朱音に言おうものなら「わかったようなことを言って」、と一笑に伏されるのがオチだろうが、颯斗は確かに知っているのだ。
高嶺がそうだったから……
あれは、時おり早智が見せるあの目は、かつて年上の幼馴染がしていたそれと同じだ。颯斗が高嶺に対して、何と言ったらいいかわからない、言葉にすらできないような、ほんの些細な違和感をおぼえるようになった矢先、高嶺は花守を出て行った。颯斗に何ひとつ告げることなく、ひとりで決めて、ひとりで出て行ってしまった。何がなんだかわからないまま、ただひとり見送ることになった颯斗。
あの時の喪失感は、今でも心の奥底にうっすらと焦げ付いている。
「まったく、厄介なことを」
あれこれ考えるのはいいが、ついついいらぬことまで思い出してしまうのはいただけない。頭を振って己を制し、吐息と共に空を見上げる。
そもそもの発端は母だ。
別にもう会いに来てくれないからといって“愛されていない”、などと言いはしない。溺愛には程遠いのかもしれないが、帰り際に「別れたくない」、そう言って駄々っ子のように泣いた、母と呼ぶにはあまりにも若い女の姿を今でも覚えている。あれもきっと愛の形、“本当”と呼ばれる複雑なものの一面には違いないのだ。
茜色がこびり付く空の下、まだ自分よりもいくらか背の高かった母の手を引き里から外界へと降りる坂道を下った、そんな思い出。
だから大丈夫。
離れていても大丈夫。
好き勝手していても許す。
許すから……
これ以上突然の思いつきで、こっちの生活を引っ掻き回すな。
今回の騒動は、無神経な母が姉の地雷原を土足で踏みしだいて行ったことに端を発する。一見したところそれは、母と姉との間で起きた問題のようにも思われるのだが、颯斗の方は颯斗でひとり思い悩むことになった。いきなり自分の好きにすればいいと言われて、正直困っている。どうしたら良いのかわからないのだ。
好きなものとは一体何ぞや。
将来の展望もなければ、着たい服ひとつ思い浮かばない。
「俺ってもしかして、思考力ゼロ?」
……マヂで?
齢十三にして、少々受け入れ難い事実との遭遇……
散歩がてらに訪れた給水等の丘で、あれこれ考えあぐねること二時間と少し。
気付けばあたりは薄暮に沈んでいたりして、肌寒さから逃れるよう引き上げて来たのはいいが、夜半になって熱を出した。